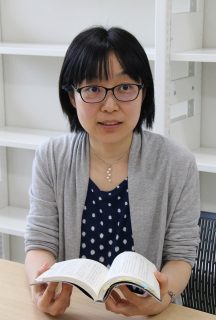
「原爆被害についてまだ語られていないことってたくさんあると思います」と話す四條さん=長崎市文教町、長崎大
日本学術振興会特別研究員 四條知恵さん(40) 語り方の変容を追う 燔祭説から悲惨さ訴えるものへ
「隠蔽(いんぺい)、排除されたものに目を向けることが歴史の可能性を開く」-。この視点を基本に、浦上地域のカトリック教界における原爆被害の語りの変容を追った著書「浦上の原爆の語り 永井隆からローマ教皇へ」(未來社刊)を2015年出版。このテーマを突き詰めようと研究を進めている。
広島市生まれ。原爆で多くの犠牲者が出た広島女学院中高が母校。原爆について特に関心があったわけではないが在学中、碑巡りで県外の高校生を案内したこともあった。早稲田大では考古学を専攻。就職の際、母が広島平和記念資料館の学芸員募集を偶然知り、応募して働くことになった。
同館で6年間勤務。啓発活動や展示の企画、調査研究に携わった。多くの被爆者に会い、「大切な家族を亡くした人にとって、被爆は今も続く現実だと実感した。それは原爆被害とは何なのかを考える今の研究にもつながっている」と語る。
結婚を機に長崎へ移住。純心女子学園の被爆体験手記集を読み、原爆死を「美しい死であったと振り返る語り」が目を引いた。長崎で原爆被害はどう受け止められてきたのか、さらに学ぼうと九州大大学院に進んだ。
同書は、博士論文に加筆修正したもの。浦上のカトリック集団にみられる原爆被害の語り方は、1981年のローマ法王ヨハネ・パウロ2世の長崎来訪を機に、原爆死を平和のための犠牲と捉える永井隆の燔祭(はんさい)説の影響から、戦争の悲惨さを語り継ぐ意義を強調するものへとダイナミックに変わっていった。その変容を実証的に明らかにした。
「ヨハネ・パウロ2世は『あなたたちは戦争の生き証人だ』と言い、原爆被害を伝えることの意味が見いだされた。原爆死の意味が美しく清らかなものから、悲惨で残酷だけどだからこそ意味のあるものへと180度転換した。理不尽な暴力を受けた後で、人が痛みを抱えてどうやって生きる意味を見いだしてきたのか。旅するような気持ちで読んでもらえたら」と語る。
同書の最後で「原爆という出来事は、われわれのなかで、変容しつつ、いまも生み出されている」と説く。「現在語られていることが全てではない。過去は固定された事実ではなく、現代の私たちがどう意味を見いだすかによって変わる。それは原爆だけでなく歴史的な出来事全般に言える」
現在、長崎の語りの特徴にさらに迫ろうと、比較対象として広島のカトリック教徒の語りを調査。あまり顧みられてこなかった障害者の原爆被害の語りにも関心が向く。「歴史と向き合う姿勢としては、語られていないことに目を向けることが大事だと思う。地道に資料発掘をして歴史を巡る研究に貢献したい」
◎著作紹介
占領期、原爆死を平和のための犠牲と捉えた燔祭説は、なぜ浦上のカトリック教界で受容されたのか。四條さんの著書=写真=は、浦上の社会情勢の変化を踏まえて分析している。
燔祭説以前、「原爆は天罰」という語りが浦上で流布。禁教期の迫害に耐えて信仰を守り続けてきた浦上の信徒にとって、それはカトリック集団としての歴史観を否定し、地域共同体の結束に「ひび」を入れるものだった。同書は、燔祭説が肉親の死に意味を与えたことで、その死を貶(おとし)める隣人とのひびを埋める役割を果たした-と指摘。信徒が求め、かつ永井隆が与えたいと願ったことが「肉親の原爆死の意味」であり、「崩れ去りそうになっていた浦上のきずなを強め、再建という方向に歩み出すことを促すものだった」と説く。
そして原爆の残酷さ、悲惨さを直接的に訴えるようなその他の語りは周辺に追いやられ、原爆被害の問題性は見えなくなってしまった。同書は「浦上の輝く『復興』を目指して語られた燔祭説が覆い隠そうとしたのは、率先して復興を導き、あるいは支える人たちのあいだで、消えることなく疼(うず)き続ける痛みでもあったのかもしれない」と指摘する。
【写真説明】
「原爆被害についてまだ語られていないことってたくさんあると思います」と話す四條さん=長崎市文教町、長崎大

